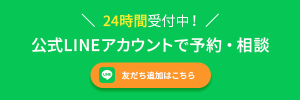冷え性対策
「冷え性の原因」と今日からできる3つのケア
季節に関わらず、冷え性でお悩みの方は女性を中心に多いです。実は、冷え性の原因は、“体質”の問題よりも、“血流の滞りが大きく影響している”ケースが多いことはあまり知られていません。
現代医学でも冷え性は、ただ体が冷えるだけでなく、ストレスや自律神経の乱れとも深く関係していると考えられています。
頭や身体がリラックスする時間が少なく、自律神経が興奮状態に偏り、血流が滞りやすいケースは現代の多くの方に当てはまるのでしょうか。
医学的な原因もよく加味した上で東洋医学は、“心と体のつながり”をとても大切にします。症状の裏に隠れた“流れの乱れ”をやさしく整える方向を考えていきます。
東洋医学の視点では、血流だけでなく「気(き)」や「水(すい)」の流れも重視します。
この流れがスムーズだと体はあたたかく、元気に働きます。逆に滞ると、“冷えやだるさ、疲れがたまりやすくなるのです”。
そこで今回は、当院の東洋医学の視点から
“今日からできる簡単な冷え性対策3つ” をお伝えします。
① ふくらはぎを動かして血流エンジンを回す
ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれてポンプのように働き、下半身にたまった血液を心臓へ押し戻す大事な役割があります。
デスクワークや立ち仕事で長時間同じ姿勢が続くこと、日常シーンで結構あるかと思います。
また、ストレスが続くと筋肉がこわばり、ふくらはぎも硬くなります。
これらのことから、ふくらはぎが硬くなると、血液がうまく戻れず、冷えを感じやすくなります。
ポイントは“動かすこと”
つま先立ちや、軽い足踏みでOK。
たった1〜2分でも血の巡りが変わり、
「なんだか気持ちも少し軽いかも」と感じられることもあります。
体を動かして“気の流れ”を作ることも大切。忙しい毎日の中でできる、小さなセルフケアです。
② 体幹の柔軟性を高めて 自律神経のバランスを整える
体幹が硬くなると、呼吸が浅くなり、ストレスが抜けにくくなります。
呼吸が浅い状態は東洋医学でいう“気が巡らない”状態と同じ。
内臓の動き(働き)に制限をかけてしまうこともあります。
胸を開く深呼吸や、上半身をゆっくり伸ばしたりひねる動き、体幹をほぐすことは自律神経、また手足への血流を整える効果があります。
特に“背中・わき腹・お腹まわり”にゆっくりストレッチをかけると、ほんの数分だけでも、「あったかくなってきた」と感じられます。
体の中心がほぐれると、全身の「めぐり」はスムーズになり、自然とあたたかさが戻ってくるのです。
③ 体幹(内臓ふくめて)を温めるシンプル習慣
やはり体を温める上で意識したいことは
“内側を温めること”
ストレスが溜まると内臓の働きが落ち、お腹まわりが冷えやすくなります。
手足をいくら温めても、体の中心が冷えているとすぐに戻ってしまいます。
おすすめは、
・お腹に手のひらを当てて温める
・深い呼吸で内臓の動きをサポートする
・お灸や温熱アイテムを活用する
シンプルですが、体の中心からじんわりと温まり、冷えにくい身体づくりにつながります。
免疫力や代謝のアップにも繋がりますよ!
東洋医学は“流れをつくる医学”
東洋医学の面白さは、症状を“部分”で見るのではなく、「全身の流れ」→「心の状態」→「生活リズム」
と、体をまるごと捉えることです。
ただ手足が冷えているだけに見えても、その背景にはストレスや疲労、内臓の働きの低下など、さまざまな要因が隠れています。
こうした「見えない流れ」を整えていくのが、鍼灸の得意とするところです。
冷えは“体からの小さなサイン”。
今日からできる3つのケアで、優しくあたためていきましょう(^^♪